掲載日:2025/3/6

「2025年の崖」という言葉をご存じでしょうか。日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れがもたらす危機的な状況を表す言葉で、2025年が間近に迫った今、改めて注目されています。
本記事では、2025年の崖問題の意味から原因、対策、現在の取組状況までをわかりやすく解説します。2025年の崖を乗り越えるためのヒントにお役立てください。
2025年の崖とは

「2025年の崖」とは、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れに警鐘を鳴らす言葉です。経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」で提唱され、注目を集めました。
2025年の崖を招く主な要因とされているのは、多くの企業で1990年代から2000年代ごろに構築された、いわゆる「レガシーシステム」です。老朽化したレガシーシステムの保守費用は年々増加し、その保守を支えてきたベテランIT技術者の多くも定年退職を迎えています。これにより、レガシーシステムの保守が立ち行かなくなることが懸念されています。
対策を講じなければ、レガシーシステムの保守にかかる費用がIT予算を圧迫し、DXへの投資が困難になるでしょう。DXの遅れは、企業の競争力を低下させる要因です。2025年が目前に迫った今、「崖」を乗り越えるために、早急なレガシーシステムの刷新とDXの推進が求められています。
2025年の崖を克服できなかった場合に待っている未来

DXレポートでは、2025年の崖を克服できなかった場合に陥る危機的な状況が示されています。
崖を克服できなかった場合に待っている、3つの未来を見ていきましょう。
ユーザー企業:デジタル競争の敗者に
2025年の崖を乗り越えられなかったユーザー企業は、デジタル競争において深刻な不利益を被る可能性があります。
レガシーシステムの残存により、ブラックボックス化したシステムではデータを効果的に活用できず、迅速な意思決定や顧客ニーズへの柔軟な対応が阻害される点が要因の1つです。また、老朽化したシステムの保守には多大なコストがかかる一方で、継承する人材の確保も困難になります。加えて、システムの老朽化はセキュリティの脆弱性を増大させ、攻撃のリスクも高まるでしょう。
こうした要因が重なり、競合他社とのデジタル競争に後れをとることで、市場シェアの低下や収益性の悪化を招く恐れがあります。
ベンダー企業:成長領域を攻めあぐねる
2025年の崖は、ITサービスを提供するベンダー企業にとっても大きな課題です。
レガシーシステムの保守ビジネスから脱却できないベンダー企業は、新しい技術やサービスの開発に十分な投資を行うことが難しくなります。AIやIoT、クラウドなどの成長領域に資金や人材を割けなければ、イノベーションの波に乗り遅れるでしょう。また、レガシースキルに特化した人材の再教育をおこなうことで、新しい技術に精通した人材の獲得が後回しになり、技術力や競争力が低下していく恐れがあります。
こうした状況は、個々のベンダー企業の成長を妨げるだけでなく、日本のIT産業全体の国際競争力にも悪影響を及ぼす危険性があるでしょう。
レガシーシステムの残存による経済損失は最大12兆円/年
DXレポートによると、2025年以降、レガシーシステムの残存による経済損失は最大で年間12兆円に達すると試算されています。
これは、2014年の日本国内でのシステム障害による損失額4.96兆円の約80%がレガシーシステムに起因している、というデータに基づいたものです(約5兆円×80%=4兆円)。システムの老朽化にともないシステム障害のリスクが3倍に増加すると推定して、4兆円×3=12兆円という数字が導き出されました。
この巨額の経済損失からも、2025年の崖はIT業界だけの問題ではなく、日本の国際的な地位の後退にもつながる深刻な問題であることがわかるでしょう。
2025年の崖を招く原因

個々の企業のみならず、日本の国際競争力にも大きな影響を及ぼしかねない2025年の崖を引き起こす原因を、もう少し詳しく見ていきましょう。
DXレポートで挙げられている、主な3つの原因を解説します。
レガシーシステムがDXの足かせに
ここまで見てきたように、多くの企業に残るレガシーシステムは、DX推進の大きな足かせです。
長年の改修や機能追加によって、レガシーシステムは複雑化・ブラックボックス化しており、新しいデジタル技術の活用を妨げています。また、保守に多くのリソースを要するため、企業は最新技術を採用したプロジェクトに人材や予算を振り向けられません。
結果として、DXが進まず2025年の崖を招くことにつながります。
経営層や現場が問題を把握できていない
経営層や現場がDXの重要性を認識しつつも、自社のITシステムの現状や問題点を正確に把握できていないことも、2025年の崖を招く原因の1つです。
レガシーシステムの複雑さや技術的負債は実態が見えにくく、具体的な対策が立てられていない企業は少なくありません。問題を認識していても、レガシーシステムからの脱却には膨大なコストと時間がかかるため、決断を躊躇しているケースもあるでしょう。
認識の甘さや決断の遅れが、2025年の崖を招くことにつながります。
DX人材不足
DXを推進するための専門スキルを持ったIT人材の不足も課題です。
AIやIoT、クラウドなどの新しい技術が急速に発展する中で、デジタル技術に精通し、かつビジネス戦略を理解して両者を結びつけられる人材が不足しています。レガシーシステムを抱える多くの企業では保守に人材を割かれ、新技術の習得や活用に十分なリソースを割けていません。
また、ユーザー企業がシステム開発や運用をベンダー企業に依存している場合も、自社のITシステムに対する理解や管理能力を失い、DX人材不足を助長する要因となります。
2025年の崖を克服するための主な対策
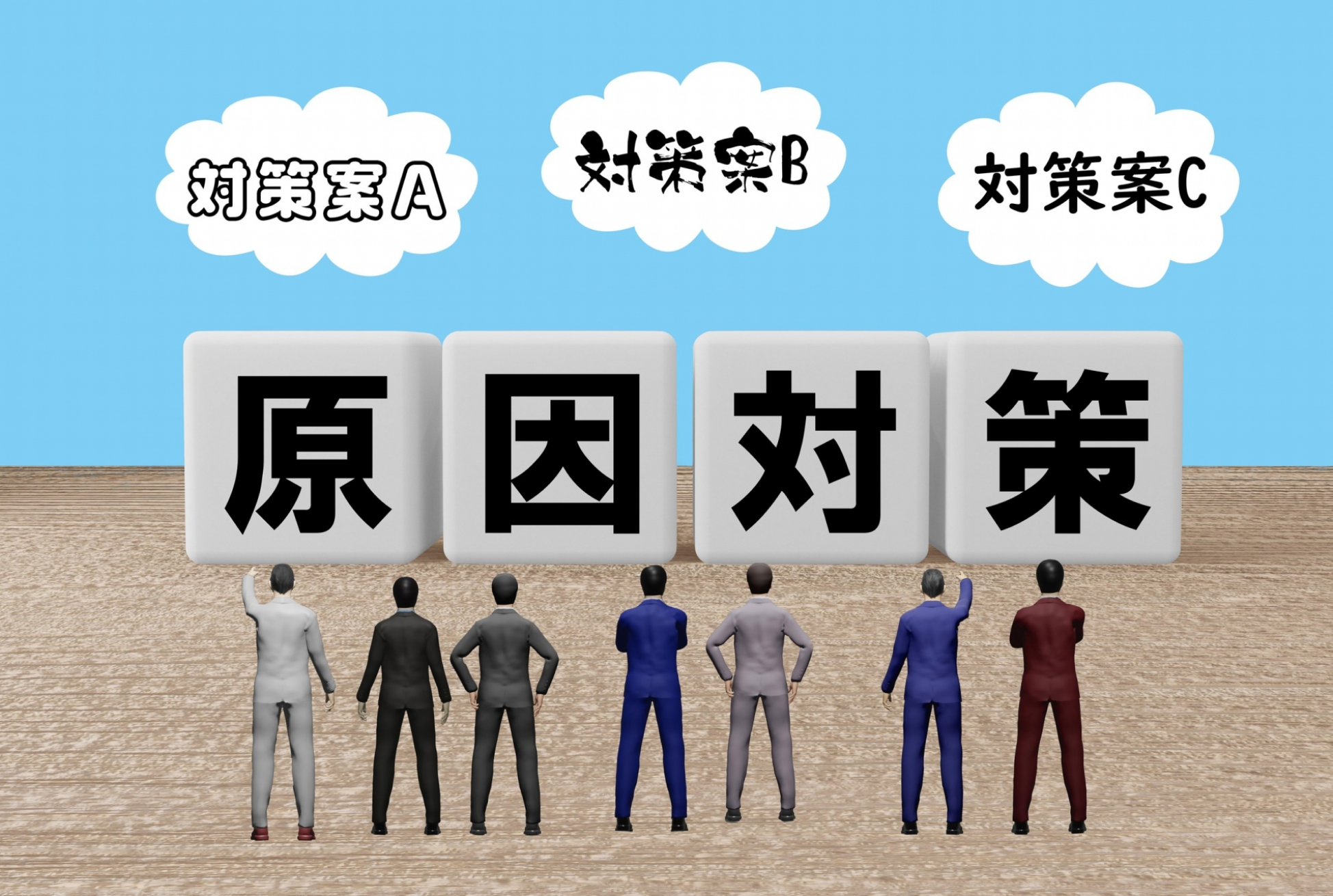
2025年の崖は、適切な対策を行うことで影響を和らげたり、回避したりすることが可能です。
DXレポートで提案されている、主な3つの対策を見ていきましょう。
レガシーシステムの仕分けと刷新
2025年の崖を克服するためには、まずレガシーシステムの適切な仕分けが必要です。
システムを「廃棄」「刷新」「維持」の3つに分類し、優先順位をつけて対応していきましょう。刷新が必要なシステムは、モダナイゼーションやマイグレーションなどの手法を用いて更新を進めます。クラウドへの移行やマイクロサービス化など、最新技術の積極的な活用により、柔軟性と拡張性の高いシステムに生まれ変わらせることが可能です。
関連記事:モダナイゼーションとは?4つの手法と失敗しないポイントを解説
ユーザー企業・ベンダー企業の新たな関係構築
従来型の開発から脱却し、ユーザー企業とベンダー企業が協力してDXを推進する、新たな関係構築も不可欠です。
新しい関係では、ユーザー企業が自社のIT戦略を主体的に立案し、ベンダー企業がその実現を支援する立場となります。また、アジャイル開発やDevOpsを導入し、両者が緊密に連携しながら、市場の変化に迅速に対応できる体制を構築することも重要です。
関連記事:『システム開発』の『工程』とは? ウォーターフォールモデルとアジャイルモデルの違い
DX人材の育成・確保
2025年の崖を克服するためには、DX人材の育成と確保も欠かせません。
ユーザー企業では、デジタル技術を活用したビジネス変革を推進できる人材の育成と確保が必要です。一方、ベンダー企業は、レガシーシステムの維持・保守ビジネスから脱却し、DX人材へのシフトが求められます。
DX人材の育成には、アジャイル開発の実践やスキル標準・講座認定制度を活用した人材育成プログラムなどが有効です。
2025年の崖を克服した先に待っている未来

適切な対策を行い2025年の崖を克服することで、企業や日本社会にはどのような変化が起こるのでしょうか。
DXレポートが示す、2025年の崖を克服した先の未来を見てみましょう。
ユーザー企業:DXによりビジネスモデルを変革
2025年の崖を克服してDXを積極的に推進したユーザー企業は、既存のビジネスモデルを変革し、新たな価値を創出できます。
例えば、効果的なデータ活用により、顧客や市場の変化に迅速かつ柔軟に対応できるようになるでしょう。また、クラウドやモバイル、AIなどの最新のデジタル技術を活用した製品やサービスを素早く市場に投入することが可能です。
このような変革を遂げたユーザー企業は「デジタル企業」へと進化し、デジタル時代の競争優位を獲得して持続的な成長を実現できるでしょう。
ベンダー企業:成長領域に人材・資金をシフトし競争力向上
2025年の崖を克服したベンダー企業は、レガシーシステムの保守から脱却し、最新の技術分野への人材や資金のシフトが可能です。
これにより、既存システムの保守業務から、高い成長が見込める新しいビジネスモデルへと転換を図れます。また、ユーザー企業との関係も変化し、単なる開発の受託ではなく、利益を共有できるパートナーシップを築けるようになるでしょう。
新しいビジネスモデルにより、ベンダー企業は継続的な収益源を確保しつつ、技術革新のスピードに柔軟に対応できるようになります。
2030年に実質GDP130兆円超の押し上げ
DXレポートによると、2025年の崖を克服してDXを積極的に推進することで、2030年には日本の実質GDPが130兆円超押し上げられると予測されています。
この予測は、総務省の「平成29年版情報通信白書」で示された、企業改革やIoT・AIの需要創出により2030年の実質GDPが132兆円押し上げられるという見通しに基づくものです。
デジタル技術を活用した新産業の創出や生産性の向上が進むことで、日本の国際競争力が飛躍的に高まることが期待されます。
2025年の崖を目前にしたDX取組状況

2024年6月、情報処理推進機構(IPA)が、「DX動向2024」でDXの取組状況を公表しました。
DXに取り組んでいる企業の割合は、2021年度の55.8%から2023年度は73.7%に増加しており、DXの波が着実に広がっていることが伺えます。
レガシーシステムの刷新状況も改善傾向にあり、「レガシーシステムがない」、または「一部のみ」と回答した企業の割合が、2022年度の40.4%から2023年度には58.0%に増加しています。しかし、4割程度の企業は、依然として「半分以上がレガシーシステム」または「把握できていない」状況です。
一方で、こうしたDXの広がりを受けて、DX人材の不足が質・量ともに深刻化していることも伺えます。
・人材の「量」
・人材の「質」
企業は外部からの人材調達を進めるほか、自社でのDX人材育成が急務です。
まとめ|2025年の崖をスキルセット見直しの機会に

2025年の崖は、日本企業のデジタル競争力に関わる深刻な課題です。
対策を怠れば、企業の競争力が低下し、日本全体でも大きな経済損失を被りかねません。レガシーシステムの刷新やユーザー企業とベンダー企業の関係再構築、人材の育成などの対策を通じて、デジタル技術を活用したビジネス変革が求められています。
企業が対策を迫られる2025年の崖は、エンジニアにとっても自身のスキルセットを見直す機会です。積極的に新技術を習得し、DXを支える人材へとシフトしていきましょう。
