掲載日:2023/03/31

『IoT』とは、モノに対しインターネットを介して情報交換する技術です。現在では多様な機器にこの技術が活用され、生活に欠かせない技術になりつつあります。本記事では、仕組みや機能、活用事例について解説します。
『IoT』とは?仕組みとメリット

『IoT』とは、直訳すると「モノのインターネット」のことを指し、身の回りの道具をインターネットを介して情報交換する技術です。「Internet of Things」を略して『IoT』と呼ばれています。
これまで、インターネットにつながっているモノといえば、パソコンやスマートフォン、タブレット端末でした。しかし、現在ではエアコンや冷蔵庫、自動車などあらゆるモノがインターネットにつながっています。
モノの状態や情報を遠隔で把握できれば、生活はより便利になるでしょう。ここでは、『IoT』の具体的な仕組みやメリットについて解説します。
『IoT』の仕組み
『IoT』は、センサーによってモノの状態や動きを把握し、そのデータをインターネットを介して届けます。IoTデバイスには、カメラや無線通信のほかに、センサーが搭載されています。
センサーは、データを取得する装置です。温度センサーや光センサー、圧力センサーなどさまざまな種類があり、IoTデバイスには取得したいデータに適したセンサーが搭載されています。
センサーでモノの動きを感知・計測して、データを定量化します。通信機能を使ってデータを送信することにより、遠隔でモノのデータが交換されます。
『IoT』はデバイスだけではなく、クラウドやアプリケーションとの連動により機能します。IoTデバイスから受け取ったデータを蓄積するのがクラウドです。クラウドからデータを受け取り、アプリケーションでそのデータを分析・命令することにより、スマートフォンやパソコンと情報交換が可能です。
『IoT』を活用するメリット
『IoT』を活用するメリットとして、以下の3つが挙げられます。
● 生活が便利になる
● 新しいサービスの誕生につながる
● 働き方改革の推進につながる
『IoT』でインターネットを介してモノとつながると、遠隔地から操作や管理が可能です。帰宅中に家電を操作したり、外出中に家の様子を確認したりと、家にいなくても家電などを操作できるため、時間や場所を気にすることなく生活できます。
また、運送や農業、医療といった日常生活と関係が深い分野にも『IoT』が浸透すれば、人材不足、地方の過疎化などの課題解決に向けた新しい商品やサービスの誕生にもつながるでしょう。
『IoT』の活用は、働き方改革の推進にもつながります。例えば、IoT技術により従業員の位置情報や施設の利用状況といった情報の取得が可能です。それにより、手間となっていた手続きや管理業務の短縮にもつながります。
他の業務にも応用すれば、業務効率化により生産性向上や労働時間短縮といった効果も期待できます。これが自ずと働き方改革の推進につながることもあるでしょう。
『IoT』に関与する通信技術

総務省によると、2020年代のうちに約450億台のIoT機器がインターネットに接続されると予測されています。必然的に通信量も増加することが予測できます。増加する通信量に対応するため、注目されている通信技術が「5G」「LPWA」です。
ここでは、2つの通信技術について解説します。
LPWA
LPWA(Low Power Wide Area)は以下の3つの特徴を持つ通信技術です。
● 省電力:一般的な電池で、数年から数十年の運用ができる
● 広範囲:数km~数十kmの通信が可能
● 低コスト:接続コストが安く、低価格で運用できる
通信速度は速くないものの、通信速度を求めない『IoT』に適した通信技術です。
5G
5Gは以下の3つの特徴を持つ通信技術です。
● 高速大容量:通信速度は最大20Gbps(4Gの約20倍)。2時間の映画を15秒でダウンロードできる
● 多数同時接続:接続機器数は100万台/km2。約1万台の端末をインターネットに同時接続できる(4Gの約10倍)
● 低遅延:遅延は1ミリ秒(LTEの約10分の1)。タイムラグを気にすることなく遠隔地にあるモノをリアルタイムに操作・制御できる
IoT化がさらに普及した場合、既存の4GやLTEなどの通信方式のままでは、データ量に耐えきれずデータ遅延の発生が予想されます。5Gの開始は『IoT』の普及を後押しするだけではなく、その膨大なデータの活用が、多くの業界や職種のあり方の劇的な変化につながるでしょう。
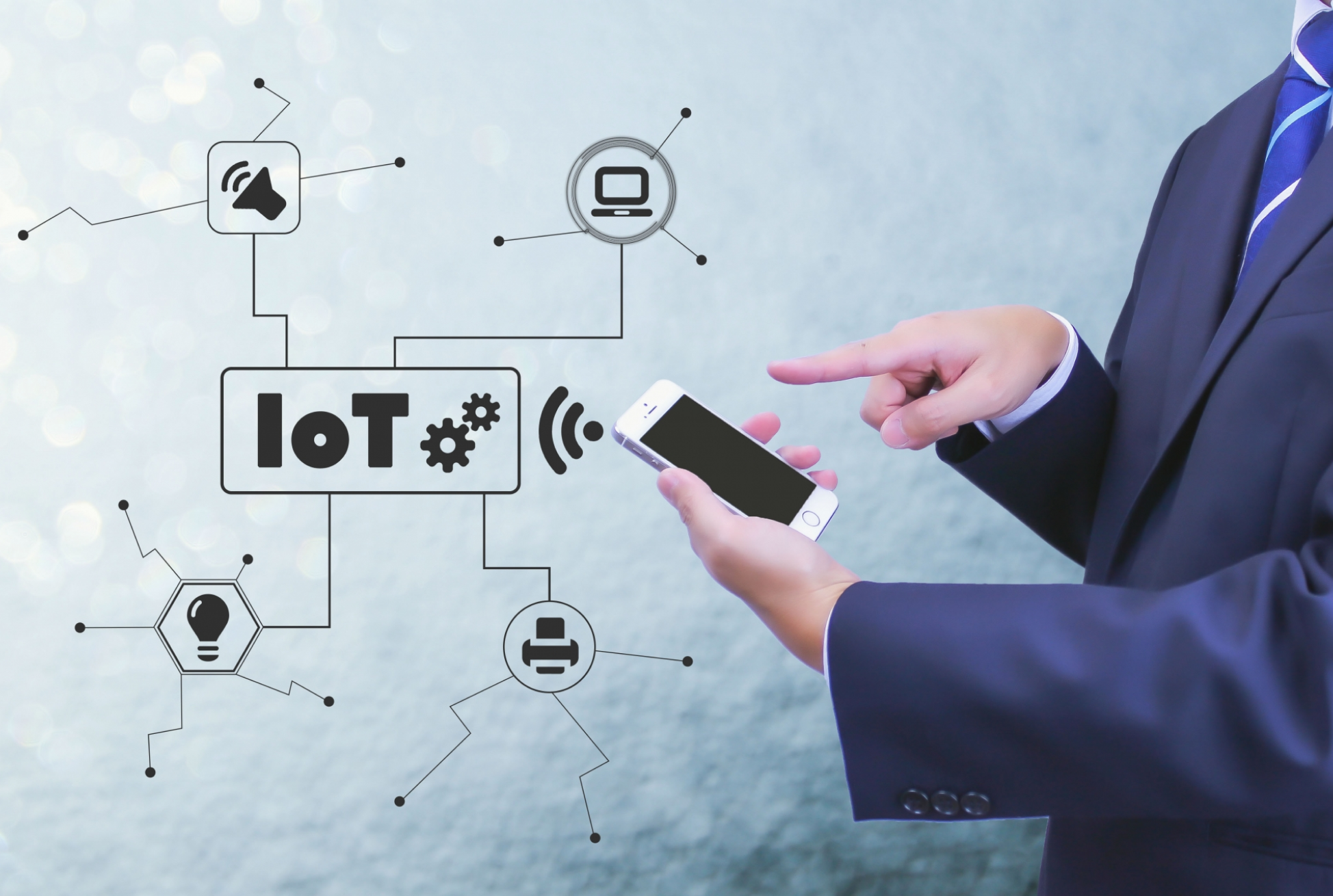
『IoT』が持つ3つの機能
『IoT』には、大きく分けて以下の3つの機能があります。
● モノの状態、動きの把握
● モノの操作
● モノ同士の通信
すべてに共通するのは、遠隔にあるモノに対して監視・操作・制御することです。これらの機能は単独で使うだけでなく、複数の機能を同時に使うケースもあります。ここでは、『IoT』の機能が持つ3つの機能について解説します。
1.モノの状態、動きの把握
1つめの『IoT』が持つ機能は、モノの状態や動きの把握ができることです。センサーから取得したデータを受信すれば、モノから離れた場所にいても状態を把握できます。例えば、『IoT』が搭載された照明があれば、外出時に家の照明の状態を確認できます。
IoTデバイスから利用頻度や利用時間といったデータの取得も可能です。メーカー側からすると、マーケティングリサーチやアンケートといった手間をかけることなくユーザーニーズを把握できます。
また、農業の分野では温度や湿度、水位などを検知し、自動で最適な環境に調節するといった活用もされています。異常や変化といった「人がアクションを起こすための情報」をリアルタイムで届ける機能と言えるでしょう。
2.モノの操作
2つめの機能は、遠隔でモノを操作できることです。インターネットを通じてIoTデバイスにアクセスすれば、離れた場所からでも電源のON / OFFや設定変更といった操作ができます。
帰宅中に自宅のエアコンの電源を入れたり、シャッターを開けたりといった操作ができます。外出先から工場の設備を動かせるため、現場に行かずに設備のメンテナンスも可能です。
離れた場所から遠隔操作可能な機能により、場所を問わずにモノを動かせるようになったことで、より便利な生活を送れたり、仕事を効率化できたりします。
3.モノ同士の通信
3つめの機能は、モノ同士の通信ができることです。代表的な事例として、エアコンの自動制御機能や自動運転技術が挙げられます。インターネットに接続したモノ同士で通信できるため、人が介在することなくモノを動かせます。この『IoT』技術は、自動化の実現には欠かせません。
例えば自動運転技術であれば、ほかの車や信号といったさまざまな機器と通信し、車の周辺状況を把握しながら走行する技術が開発されています。信号機も『IoT』になれば、道路の混雑具合を検知した上で時間を調整し、渋滞を緩和させるといった対応もできるでしょう。

【分野別】『IoT』の活用事例3選
『IoT』は、医療や製造、交通などさまざまな分野で活用されています。どの分野でも、利便性や効率が向上するだけではなく、人材不足問題の解消にも役立つでしょう。ここでは、分野別の『IoT』活用事例について解説します。
1.医療分野における『IoT』活用
医療分野での『IoT』は「IoMT(Internet of Medical Things)」と呼ばれ、デバイスとして着用型ウェアラブルデバイスが普及しています。ウェアラブルデバイスは、脈拍や心拍数、血圧といった患者の生体データの計測が可能です。
遠隔地でも健康状態や機器の動作状況をリアルタイムで把握できるため、患者が通院する必要がありません。日々の健康管理や病後のリスク管理だけではなく、在宅医療や医師不足問題にも有効です。
医師の労働環境改善への効果も期待できるでしょう。
2.製造分野における『IoT』活用
製造分野は、『IoT』が積極的に活用されている業界です。多くの企業が「スマート工場」の確立に取り組み、工場内の設備や管理システムをインターネットに接続し、データを収集しています。
設備の稼働状況を監視することにより、作業員の動きを分析したり、設備が故障する予兆を検知したりできるため、工場の生産性向上が期待できます。また、製品に対して『IoT』の機能を搭載すれば「最適な使い方の提案」「メンテナンス時期を通知」といった、ユーザーに役立つ情報の提供も可能です。
3.交通分野における『IoT』活用
交通分野では、公共交通機関やタクシー業界で『IoT』の導入が普及してきました。具体的には、バス停にあるQRコードによる運行状況の把握や、タクシー配車アプリケーションを使ってタクシーを手配するといった活用方法があります。
また、近年ではアプリケーションを使って渋滞状況や電車の遅延状況もわかるようになっており、ユーザーが効率的に移動できる仕組みが確立されています。

『IoT』の課題と将来性
IoT導入を進める上では、IT人材の不足という大きな課題があります。日本の企業全体が抱える課題であり、人材育成とともに外部との連携が鍵を握ります。
また、『IoT』との相乗効果が期待されているのがAIです。『IoT』とAIを組み合わせることにより、現在では想像もつかない機能が開発される可能性も考えられます。ここでは、『IoT』を導入する上での課題、将来性について解説します。
課題はIoTを導入するIT人材の不足
『IoT』の課題は、IT人材の不足です。現在の日本では、業種を問わずIT人材が不足しているため、『IoT』を導入しようとしても、それを推進する人材がいません。
『IoT』の導入には、IoTデバイスやクラウド、アプリケーションに対する知識だけではなく、データを分析するデータサイエンティストとしての能力も求められます。そのような知識を持っている人材は簡単には見つかりません。特にその傾向は中小企業で強く、『IoT』の導入が進まない原因のひとつになっています。
自社で無理にIT人材を確保するのではなく、実績が豊富な外部企業と連携し、共同でIoT導入を進めるのもひとつの方法です。
AIとの相乗効果が期待される
『IoT』とAIは、相乗効果が期待できる関係性です。IoT化が急速に普及した場合、あらゆるモノがインターネットに接続し、データ化される時代になります。それにより、これまでとは比べものにならない規模のビッグデータが収集されることが予想できます。
そのデータを人間だけで分析・活用するのは困難です。しかしAIであれば、どのようなビッグデータも短時間で解析できます。それをもとに新しいAIモデルがIoTデバイスに搭載されれば、従来の機能を超えるモノができる可能性も考えられるでしょう。

まとめ:『IoT』は豊かな未来を担う技術
『IoT』とは、身の回りのモノをインターネットを介して情報交換する技術です。現在ではエアコンや冷蔵庫、自動車などあらゆるモノがインターネットにつながるようになっており、その数は、2020年代のうちに約450億台まで増加すると予測されています。
『IoT』は、医療や製造、交通などさまざまな分野で活用されていますが、現在の日本では、IT人材の不足が大きな課題です。人材育成とともに外部との連携がIoT普及の鍵を握ります。
また、『IoT』との相乗効果が期待されているのがAIです。『IoT』とAIの組み合わせにより、想像もつかない機能が開発される可能性も考えられます。豊かな未来を担う技術として『IoT』の導入を推進しましょう。
