掲載日:2023/01/06
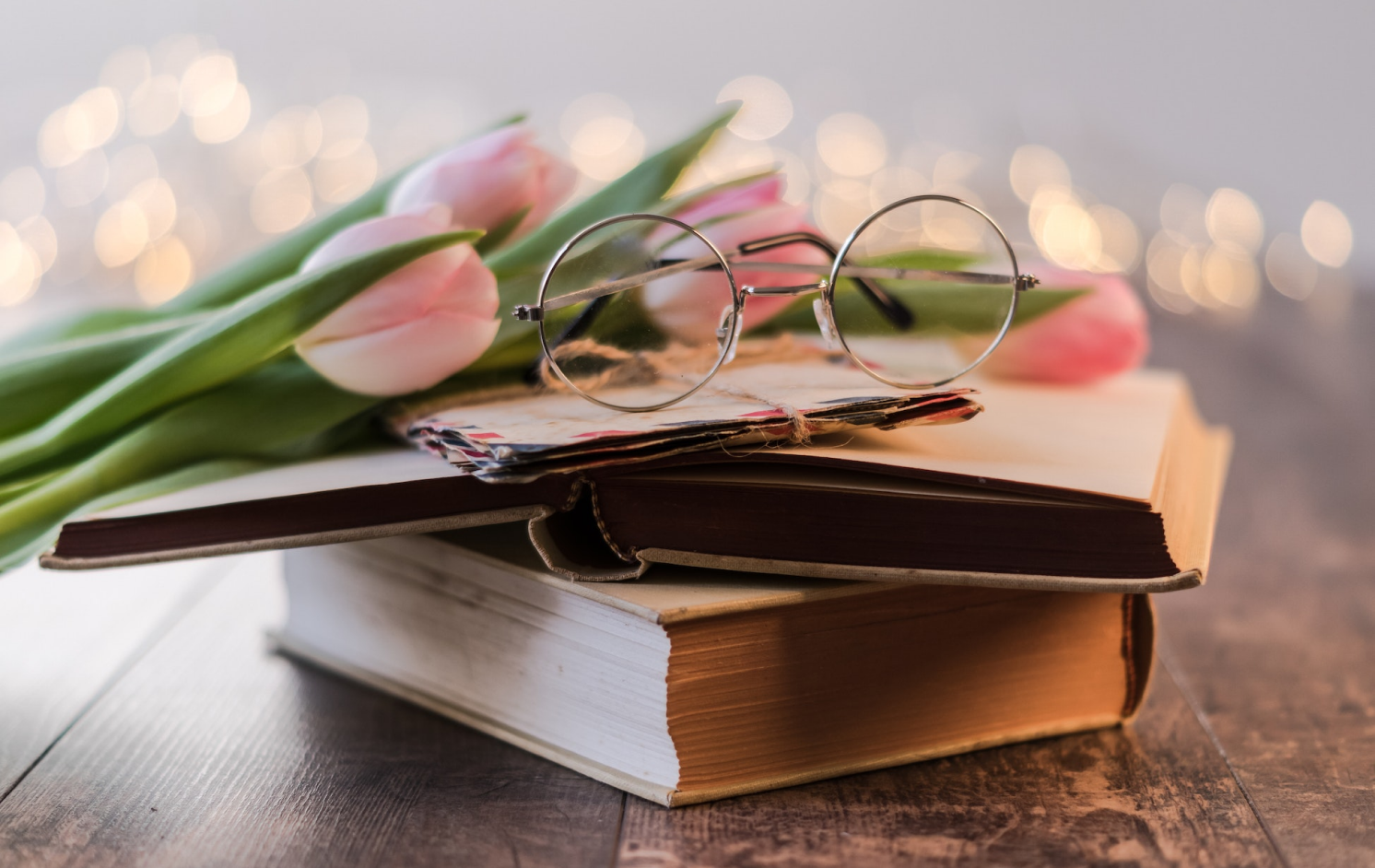
近年、役職定年が注目されるようになりました。とくに上場企業では、比較的多くの企業で導入しています。今回は、この制度がどのようなものか、上場企業で導入された背景、将来のキャリアやSBテクノロジーでの対応に関する情報などを解説します。

役職定年とはどういうもの?
近年、定年年齢が引き上がりつつあり、シニア世代の活躍が推進されています。また、労働条件環境の多様化が進み、さまざまな働き方やキャリアとの向き合い方がされるようになりました。一方で、NECなど役職定年制度を廃止する企業が増えていて、制度に注目が集まっています。
役職定年とは、ある一定の年齢以上になった際に役職を降りると定めている人事制度のことです。課長や部長などの管理職に就いている社員が対象で、その方の能力にかかわらず一律で役職を離れます。
役職定年の制度は、企業によってさまざまです。部長級や課長級の役職に就いている方の役職定年年齢の場合、55歳と設定している企業の割合がとくに多く、その次に57歳が設定されていました。このように、基本的には50代後半の年齢に設定されていることが多いようです。
ただし、役職定年が導入された時代からは労働環境が大きく異なっています。60歳で定年する社員が一般的な時代に役職定年が導入されたため、65歳で定年する方が増えつつある今の時代の実情にはあわなくなっているかもしれません。
人事院が民間企業の勤務条件制度などを調査し発表したデータで、役職定年に関する内容が確認可能です。その『平成29年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』という調査では、従業員が50人以上いる企業4,228社を対象として調べられました。
そのデータによると、役職定年制度があるのは全体で16.4%、企業規模500人以上の比較的規模が大きい企業では30.7%でした。このことから、規模が大きい企業のほうが、積極的に役職定年制度を採用していることがわかります。
役職定年制度は、組織活性化の観点から実施されることの多い人事制度です。制度を導入している企業によっては、どのような能力開発を進めるのかを含めて、役職定年を迎える従業員も想定した長期のキャリアプランを立てている企業もあります。
役職定年後におこなう業務はその社員によって異なり、一般職や専門職などを任されます。今までに培った知識をいかせるような業務を役職定年後におこなうケースがある一方で、場合によってはこれまでとまったく違う業務を任されるケースもあるようです。
役職定年をした社員は長年の経験を持っているため、新しい役職者のサポートにつけて、指導役としてキャリアや専門性をいかせるようなポジションにするケースもあります。新たな専門職を設置したり、新しい働き方を構築したりと、企業ではさまざまな方法で役職定年者のスキルをいかそうとしているのです。

上場企業で役職定年制度が導入された背景
先述のとおり、規模が大きな企業のほうが、積極的に役職定年制度を導入している傾向があります。
近年では人生100年時代だと言われており、シニア世代の働き方が注目されています。定年となる年齢が引き上げられるようになり、企業ではキャリアを積んだ人材により長く働いてもらえるようになりました。
2025年4月以降は65歳定年制が義務化されます。さらに、65歳から70歳までの就業機会確保を目的として、2021年には『高年齢者雇用安定法』が制定されました。これによって、70歳までの定年引き上げや定年制の廃止、再雇用制度や勤務延長制度による70歳までの継続雇用制度の導入などの変更があります。
定年となる年齢が引き上げられると雇用期間が長くなるため、従来の人件費よりも支払い額が高くなり、企業経営が苦しくなります。役職に就いたままの期間が長くなるケースも増えてしまうため、人件費を調整する目的で役職定年を導入している企業も存在します。
また、年功序列や終身雇用制度が崩壊しつつあり、成果主義を採用する企業が増えたことも関係があります。年功序列によってポストに就いた社員を役職定年により管理職ではなくして、あいたポストに優秀な人材を登用・昇進して成果主義の体制にできることなども、役職定年制度が導入された背景です。
とはいえ、現在ではNECなどのように役職定年制度を廃止する企業が増えています。上場企業などで役職定年制度が廃止されつつある背景は、役職定年を迎えた社員が仕事へのモチベーションを低下させてしまいかねないことへの配慮です。本来の定年まで十分に能力を発揮できるようにと、役職定年制度の見直しがおこなわれています。

SBテクノロジーで役職定年で働き方や仕事はどう変わるのか
一定以上の年齢になった場合に管理職から退くこととなる役職定年を取り入れると、新陳代謝を促せる上に人件費を抑えられるようになります。また社員にとっても、優秀な人材の成長機会を作り若手を育成するための環境が生まれること、年齢が上がって体力が低下しても無理なく働ける職場になることなどがメリットです。
役職に就いている方は、部署や課全体の成績に対する責任があるため、仕事に対して感じるプレッシャーが重い傾向にあります。そのため、役職定年を迎えることで責任範囲が減少し、プレッシャーを減らせる点も魅力です。役職定年を迎えたことで役職を引き継いだ方の育成にも役立ちます。
ただし一般的な役職定年では、役職を降りてから仕事の意欲が低下してしまう社員が多いようです。50歳代前半など、早めの年齢で役職定年となった方のほうがその傾向が大きいと言われています。役職定年後、部下から相談を受けなくなるなどでコミュニケーションが減り、職場で孤立してしまうケースにも注意が必要です。
さらに、役職定年者の意欲が低下してしまうことで、それを見た周りの社員にとっても今後のキャリアプランの目標がなくなってしまいかねません。このように、役職定年にはさまざまなメリットがある一方で、実はデメリットも大きい制度だと言えそうです。
役職定年制度を導入している企業で働く場合には、以下のようなことを考えておくといいでしょう。
● 今後のキャリアを考える機会としてキャリアデザイン研修を受講する
● 周囲からの感謝など、給与やキャリア以外のやりがいを持つようにする
しかし、SBテクノロジーならば、マネージメント職とプロフェッショナル職の2つから自身のキャリアプランをを選べるようになっています。ラインマネージメントから現場に戻りたい方にも門戸を広げていて、自身にあった仕事を選択可能です。
そのため、管理職として活躍している方が役職定年で役割を下げ、一般社員として活躍するのではなく、いつでもプロフェッショナル職のキャリアに戻るという選択ができます。
また、高度プロフェッショナル職という、一定の役割以上を担う事ができる方を対象とした年齢に関係なく、高度な専門性を発揮し続けることができるキャリアパスも用意されています。対象となった社員は、定年を迎えた後の再雇用時にも処遇を変えることなく、大規模プロジェクトのプロジェクトマネージャーやITコンサルタント、PMOとして活躍することが可能です。年齢に関係なく、担うミッションによって処遇を決定するジョブ型の人事制度の考え方が反映されたこれからの時代に合った制度であると言えます。

SBテクノロジーで役職定年で給与は変わるのか
一般的な役職定年では、管理職から降りることで給与が下がってしまう傾向にあります。役職定年は、企業への貢献度や達成した成果がどうであっても、一律で役職から外されて給与が下がってしまいます。
そのことで会社への不信感につながってしまったり、もう会社から期待されてないと感じてしまったりしかねません。モチベーションの向上につなげるためには、役職定年者が自らキャリアを選択できる環境を整えることが重要です。
SBテクノロジーでは、先述したとおり自分にあったキャリアを選択できます。さらに、管理職としての立場=『マネジメント領域』を離れることになっても、『マネジメント領域』と『プロフェッショナル領域』での給与差がありません。エンジニアファーストな給与体系をとっているため、エンジニアも役職者でも給与の格差はなく、仕事の責任に応じた十分な給与が支払われます。
『マネジメント領域』とは、一般的な管理職として部下の育成や組織の戦略策定、チームの数値の責任を負うキャリア形成をおこなうものです。一方で『プロフェッショナル領域』は、テックリードとして、もしくは顧客に近い位置でプロジェクトを推進していくことを中心としたキャリアを形成できます。
これらふたつのキャリアパスがあることが、SBテクノロジーの特徴です。多様な働き方と挑める環境を用意して、どちらのキャリアにしたとしても給与体系に差が生まれない評価制度を取り入れています。

まとめ:役職定年を理解して、自身にあった仕事を選ぼう
役職定年が近年注目されており、とくに上場企業では比較的多くの企業でこの制度を導入しています。
部長級や課長級の役職に就いている方の役職定年年齢の設定は55歳としている企業が多く、その次に57歳が設定されています。基本的には、役職定年年齢を50代後半に設定していることが多いようです。
上場企業などで役職定年制度が導入された背景は、定年年齢引き上げや『高年齢者雇用安定法』の制定、年功序列制度や終身雇用制度が崩壊しつつあることなどがあります。
役職定年を取り入れると、若手を育成するための環境が生まれること、年齢が上がって体力が低下しても無理なく働ける職場になることなどがメリットです。
一方で、役職定年者の意欲が低下してしまうなどのデメリットもあるため、役職定年を取り入れた企業に勤める際には注意が必要です。また、役職定年後、職場で孤立してしまうケースや、周りの社員にとっても今後のキャリアプランの目標がなくなってしまいかねないというデメリットがあります。
SBテクノロジーでは、一律で決められるのではなく自分にあったキャリアを選択できます。さらに、管理職としての立場から退くことになっても、『マネジメント領域』と『プロフェッショナル領域』での給与差がありません。働きやすい環境で十分な給与をもらえる企業だと言えるでしょう。
