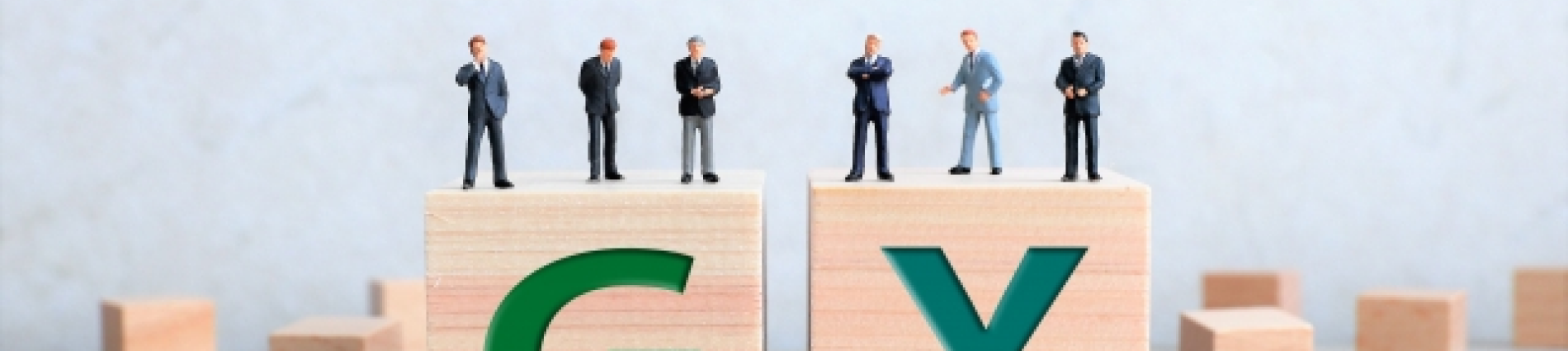掲載日:2024/11/21

地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する近年、「GX(グリーントランスフォーメーション)」への注目が高まっています。しかし、GXという言葉を聞いたことはあっても、その意味や内容はよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
環境保全と経済成長の両立を目指すGXは、ビジネスや社会を持続可能なものにする上で欠かせない取り組みです。
本記事では、GXの意味から求められる背景、政府や企業の具体的な取り組みまでを分かりやすく解説します。
GX(グリーントランスフォーメーション)の意味
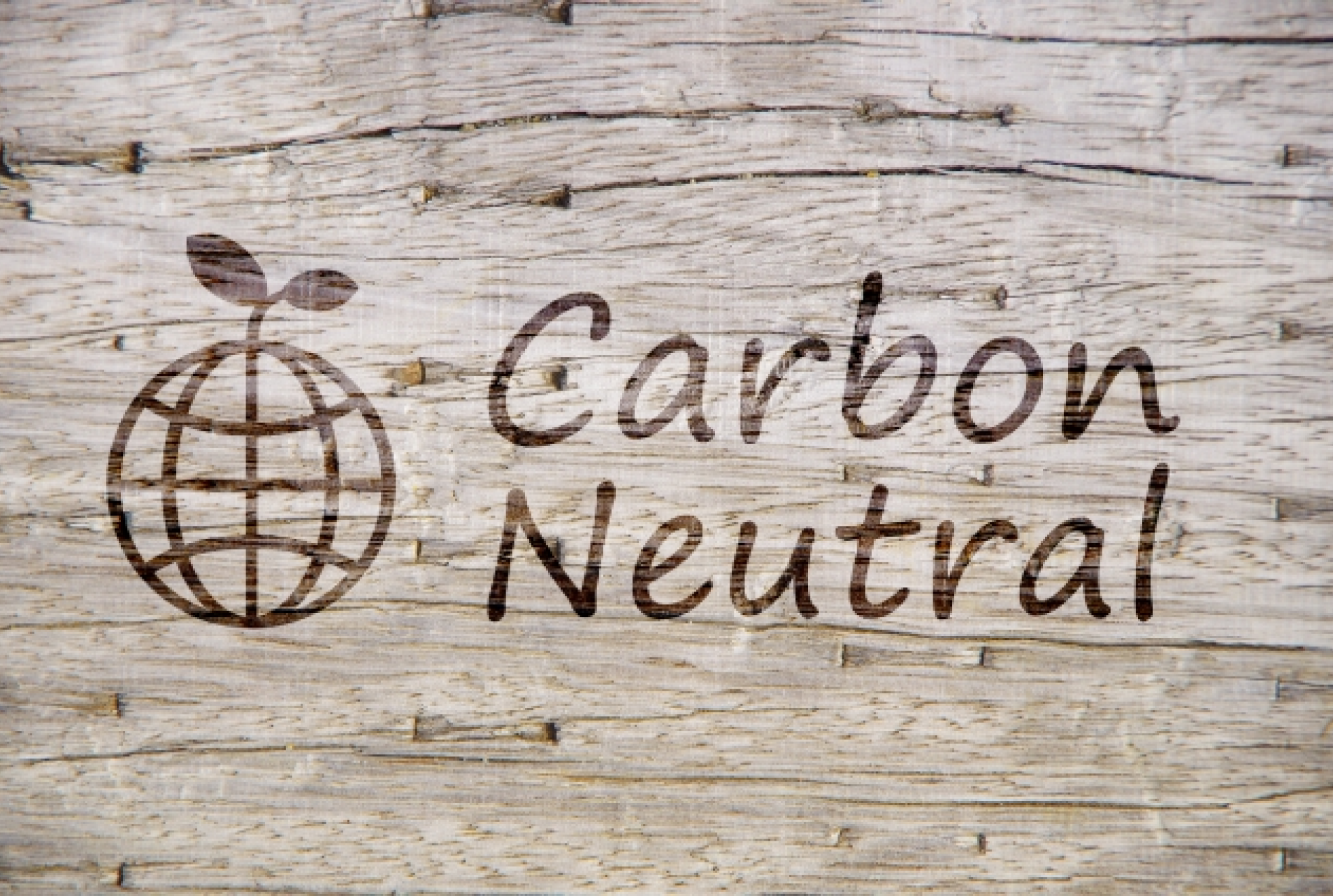
「GX(グリーントランスフォーメーション)」とは、化石燃料の使用を抑え、再生可能エネルギーなどのクリーンなエネルギーを活用する社会への転換を図る活動を意味する言葉です。
デジタル技術を活用してビジネスや社会を変革する「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は広く浸透してきましたが、GXはその「環境保全」版と捉えると良いでしょう。
GXは単なるエネルギー源の置き換えだけではありません。環境への配慮と同時に、経済成長や産業競争力向上との両立も目指す取り組みです。
日本は2050年までにカーボンニュートラル実現を宣言
2020年10月に、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言しました。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることです。「全体として」とは、排出量と吸収量のプラスマイナスを意味します。
人間が経済活動を行う上で、温室効果ガスの排出を完全にゼロにすることは困難です。そのため、例えば、化石燃料の使用を削減して温室効果ガスの排出を抑えつつ、森林保全やCO2の地下貯蔵などによる吸収を促進することで、排出量と吸収量のプラスマイナスをゼロに近づけていきます。
GXが求められる背景

近年、GXの取り組みが注目を集める背景には、地球環境の急速な悪化や、それに伴う社会や意識の変化があります。
GXが求められる4つの主な背景を解説します。
地球温暖化・気候変動の抑制
GXが求められる背景の1つは、深刻な地球温暖化と気候変動の問題です。
異常気象や海面上昇、生態系の破壊など、地球温暖化の影響は多岐にわたり、年々深刻化しています。このまま温室効果ガスの排出を続け、地球環境の悪化が進めば、人類の存続さえも危ぶまれる事態になりかねません。
危機的な状況を緩和・回避するためには、エネルギー効率の向上やクリーンエネルギーの導入などを通じた温室効果ガスの削減が急務となっています。GXは、こうした地球規模の課題に対応するための重要な取り組みです。
国際的な取り組みへの協調
GXには、国際的な取り組みと足並みをそろえる背景もあります。
2015年に採択されたパリ協定においては、世界共通の長期目標として、産業革命以前の水準に比べて地球温暖化を2℃未満、できれば1.5℃未満とすることが掲げられました。目標達成に向け、世界各国ではさまざまな脱炭素化政策が進められています。
日本も、世界に対して温室効果ガス削減やカーボンニュートラルを目指す取り組みを積極的に発信・提案し、国際社会と協調してGXを推進しています。
持続可能な成長を実現
地球の資源や環境を犠牲にした経済成長はもはや持続不可能であるという認識の広がりも、GXが注目される背景の1つです。
近年は、SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資などの、環境・経済・社会のバランスを保つ取り組みへの関心が高まっています。企業にとっては、環境への配慮は単なる制約ではなく、新たなビジネスやイノベーションを生み出すチャンスです。
環境配慮の社会的責任を果たすことが経済的なメリットをもたらすため、GXの広がりは、持続可能な社会の実現につながります。
地政学的リスクの高まり
GXが求められる背景として、近年の地政学的なリスクの高まりも無視できません。
ウクライナ戦争や中東情勢の不安定化は、世界のエネルギー市場に大きな影響を与えています。資源の多くを輸入に頼る日本にとって、世界的なエネルギー価格の高騰は、産業やビジネスの不安定さを招く大きなリスクです。
省エネ技術の導入やクリーンエネルギーの活用によって化石燃料への依存度を減らすGXは、環境保護だけでなく、エネルギー安全保障の観点からもいっそう重要な取り組みとなっています。
政府によるGX推進の主な取り組み

GXの意味や注目される背景を理解したところで、具体的な取り組みを見ていきましょう。
まずは、国全体のGXの方針を定め、企業の活動をサポートする、政府の取り組みの中から代表的な4つを紹介します。
GX実行会議
GX実行会議は、日本政府がGXの実行に必要な施策を検討するため、2022年7月に官邸に設置した会議です。内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚や幅広い分野の有識者で構成されています。
GX実行会議では、エネルギーの安定供給に向けた方策や、脱炭素化・産業構造の変革を目指したロードマップの策定などが議論されています。また、関係省庁間の連携を強化し、民間業者との協力を通じて、社会全体でのGX推進を図ることも重要な役割です。
GXリーグ
GXリーグは、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、GXを通じて持続可能な成長を目指す企業が集まり、議論や検討を行うための枠組みです。
経済産業省が中心となって2022年に構想が発表され、2023年に正式な活動を開始しました。2024年度には、747者が参画しています。
GXリーグの主な活動は、自主的な排出量取引の実践や市場創造のためのルール形成、新たなビジネス機会の創発などです。企業主導のGX推進を加速させ、カーボンニュートラル実現に向けた重要な役割を果たすことが期待されています。
GX経済移行債
GX経済移行債は、GX推進法に基づき、巨額のGX投資を実現するために、2024年2月から発行が開始された債券です。10年間で20兆円規模の発行が予定されています。
調達された資金は、省エネ機器の普及や浮体式洋上風力発電の開発・導入、炭素循環型生産体制への転換など、GX関連のさまざまな事業に活用される予定です。GX経済移行債は、日本の脱炭素社会への移行を財政面から後押しする重要な役割を担います。
GX推進のための補助金
政府は、大企業だけでなく中小企業や中堅企業でもGXを推し進めるため、さまざまな補助金制度を設けています。
例えば、既存の省エネ補助金に、脱炭素化につながる電化・燃料転換を促進する新たな類型が設けられました。また、ものづくり補助金や事業再構築補助金では、GXに資する革新的な製品やサービスの開発、グリーン分野への業態転換などを支援しています。
こうした補助金制度により、中小企業や中堅企業もGXの取り組みに積極的に参加できる環境が整えられています。
企業によるGX推進の主な取り組み事例

ここまで見てきた政府の舵取りや財政面の支援に基づいて、個々の企業が具体的にGX推進に取り組んでいます。
続いては、企業によるGX推進の主な取り組み事例を見ていきましょう。
再生可能エネルギーの利用
企業のGX推進において、再生可能エネルギーの利用は代表的な取り組みの1つです。
再生可能エネルギーの利用により、化石燃料の使用を減らし、温室効果ガスの排出を削減する効果があります。具体的には、自社施設に太陽光パネルを設置して太陽光発電を行ったり、風力発電やバイオマス発電へ移行したりするなどの取り組みが代表的です。
ただし、再生可能エネルギーの導入は初期投資コストが高いことや、安定的なエネルギー供給が難しいことなどの課題があります。設備の普及や技術の進歩により課題が解消されていけば、より導入が進むでしょう。
サプライチェーンの脱炭素推進
製品の原材料調達から製造、出荷、配送まで、サプライチェーン全体で排出量の可視化と削減を図る取り組みを進めている企業もあります。
サプライチェーン全体での取り組みは、単に自社の温室効果ガス排出量を削減するだけでなく、業界全体での脱炭素化を加速させる上で重要です。例えば、サプライヤーへの環境基準の設定・監査や、低炭素型の輸送手段への切り替えなどの取り組みがあります。
サプライチェーン全体の環境パフォーマンスを高めることで、持続可能な社会の実現に近づくことが期待されます。
循環型ビジネスモデルの構築
循環型ビジネスモデルの構築も、GX推進の有効な取り組みの1つです。
循環性の高いビジネスモデルへの転換によって、事業活動の持続可能性が高まり、新たなビジネスチャンスにもつながります。具体的な取り組みとして、製品のリサイクル・リユースシステムの確立やシェアリングサービスの導入などが代表的です。
廃棄物を減らし資源が循環することで、環境負荷を軽減すると同時に、社会のニーズに応えて経済的にも好循環を生み出すことが期待できます。
従業員教育・意識改革
企業全体でGXを効果的に推進するためには、経営層から現場の従業員まで、GXに対する理解と意識の向上を図ることが不可欠です。
GXリーグでは、GXを推進する人材のスキル標準(GXSS)を策定し、必要な知識やスキルの明確化を計っています。GXSSの活用などを通じて高度なGX人材を育成し、企業全体で組織的に取り組むことが重要です。
GXが企業文化として定着すれば、一時的な取り組みに終わることなく、長期的に持続可能な経営が可能になります。
まとめ|GXはカーボンニュートラルの実現に欠かせない取り組み

GXは、カーボンニュートラルを目指す上で欠かせない重要な取り組みです。政府や企業の取り組みを通じて、再生可能エネルギーの活用やサプライチェーンの脱炭素化、循環型ビジネスモデルの構築などさまざまな形で推進されています。
私たち一人ひとりがGXの意味や背景を理解し、企業や社会の一員として取り組むことで、環境と経済を両立した持続可能な未来の実現が近づくでしょう。