掲載日:2024/7/24

量子コンピュータとは量子力学の原理を用いたコンピュータのことです。従来のコンピュータでは容易に導き出すことのできない計算を、短い時間で処理することができるコンピュータとして、近年注目されています。
「量子コンピュータ」という言葉は知っているものの、概要や今後の実用化について知らない人も多いのではないでしょうか。この記事では、量子コンピュータとは何か、従来のコンピュータとの違いなどをわかりやすく解説します。量子コンピュータについて知りたいエンジニアの方は、ぜひ最後までご覧ください。
量子コンピュータとは

量子コンピュータとは『量子力学』を用いて情報を処理するコンピュータのことを指します。
そもそも量子とは粒子の性質と波の性質を併せ持つ、物質を形作っている最小単位です。量子は粒子と波の性質が重なり合っているため、従来の力学であるニュートンの運動法則などが通用しません。そこで、量子には『量子力学』という量子特有の動きのルールが適用されます。
前述した通り、量子は粒子と波の両方の性質が重なり合っており、粒子と波の性質の重なり合いを『量子重ね合わせ』といいます。量子コンピュータは、この重ね合わせを利用して複数の計算を同時に行うことが可能です。
従来のコンピュータとの違い

従来のコンピュータとの大きな違いは計算方法です。従来のコンピュータは、1つのビットが『0』または『1』の2進法で計算を行うため、nビットの場合は2のn乗通りの計算が個別で必要になります。
一方、量子コンピュータは1つの量子ビットで『0』かつ『1』の状態を表すことができます。量子コンピュータでは、2のn乗通りの計算を個別ではなく並列的に行えるため、従来コンピュータよりも早く処理できます。
ただし、量子コンピュータは従来コンピュータより必ずしも優れているわけではなく、従来コンピュータを使用した方がよいケースがあることは知っておきましょう。
量子コンピュータの種類は2種類
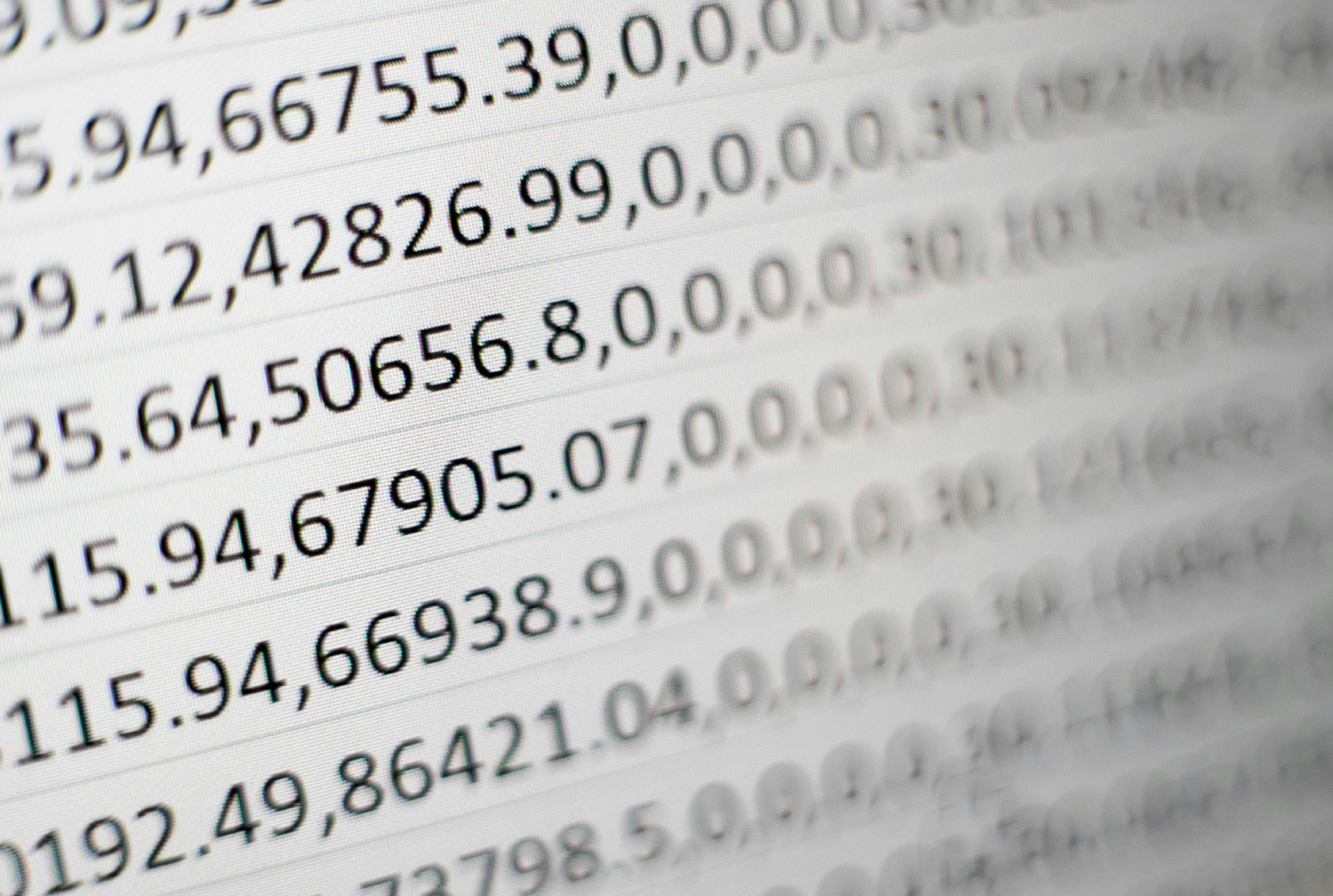
量子コンピュータは2種類の方式があります。
● 量子ゲート方式
● 量子アニーリング方式
それぞれ詳しく見ていきましょう。
量子ゲート方式
量子ゲート方式とは量子計算に特化した電子回路『量子ゲート』を用いた方式です。
『量子ゲート』は従来のコンピュータでいうところのAND、OR、NOTなどのゲートにあたります。量子ゲート方式は汎用性が高く、新素材開発や金融分野など、さまざまな分野で活用できると期待されています。
しかし実際には量子ビットは外部からの影響を受けやすく、量子重ね合わせの状態を保つことが難しいためエラーが発生しやすいのです。実用化には課題も多く、現在も開発が進められています。
量子アニーリング方式
量子アニーリング方式とは上記の量子ゲート方式とは異なり、最適化問題を解くために特化した方式です。
アニーリングとは日本語で『焼きなまし法』といって、金属を高温にしたのち、ゆっくりと冷やすことで最も安定した状態を作り出す手法のことです。量子アニーリング方式では、この焼きなまし法を量子に応用して、最適解を導き出します。
量子アニーリング方式はパラメータを設定するだけで計算できるため、プログラミングを必要とする量子ゲート方式よりも扱いやすく、すでに一部実用化されています。
量子コンピュータの実用化

従来のコンピュータでは実現できなかった規模の計算を可能にすると期待されている量子コンピュータは、今後どのように実用化されていくのでしょうか。
ここでは量子コンピュータの実用化について紹介します。
● 交通最適化
● 新薬開発や新素材(材料)の開発
● 機械学習の高度化
● 金融
● 災害対策
それぞれ詳しく見ていきましょう。
交通最適化
量子コンピュータの実用で期待されているものの一つに、車の渋滞の解消があります。
従来コンピュータでも空いている道への誘導はできるものの、誘導した先で新たに渋滞が起こってしまうこともありました。
量子コンピュータであれば、目的地までの最適ルートを従来コンピュータよりも早く導き出せます。また、その後の交通状況の予測まで行えるため、誘導した道の混雑も防ぐことが可能です。
現在実用化までには至っていないものの、実証実験が進められています。
新薬開発や新素材(材料)の開発
量子コンピュータは、新薬開発や新素材(材料)の開発にも活用されています。
新薬開発では通常、分子同士を組み合わせて、それらがどのように作用するのかをシミュレーションしています。量子コンピュータを活用すれば、各原子に量子ビットを割り当て、条件を変えながらシミュレーションすることが可能です。通常分子の数が増えるほどシミュレーションに時間がかかりますが、量子コンピュータを使用すれば、シミュレーションの時間が短縮できます。
海外では量子コンピュータを活用した新薬開発がすでに進められており、今までよりも短い期間で創薬できたという成果が出ています。
また、新素材の開発にも期待が高まっています。例えば、太陽光発電バッテリーのエネルギー変換効率が従来のものより優れた素材を探すこともできるでしょう。
機械学習の高度化
現在、量子コンピュータと機械学習を掛け合わせた『量子機械学習』が注目されています。
前提として、機械学習は大量のデータを効率的に処理しなければなりません。大量のデータを効率的に処理することに向いている量子コンピュータを掛け合わせることで、取り扱えるデータ量と学習回数が増え、機械学習を高度化させることが可能とされています。
日本では大阪大学にて量子機械学習の研究が進められ、世界最大規模の量子機械学習を実現した事例もあります。
金融
金融商品は値動きが激しく、リスクやリターンを予測するためには非常に多くの計算が必要となり、従来のコンピュータでは限界があります。
量子コンピュータを利用することで、顧客の財務状況や契約状況から最適な商品の提案ができたり、現在価格や各手数料から最大リターンを実現する金融商品の組み合わせを構築できたりするとされています。
金融部門では他にも、詐欺の検知やコンプライアンスチェックなど、さまざまな面で応用できるとされているため、今後の動向に注目しましょう。
災害対策
量子コンピュータを災害対策に役立てようという動きがあります。
地震や津波などが発生した場合、速やかに安全な場所へ避難することが重要です。しかし、実際は避難経路が途中で通れなくなっていたり、一部の避難所へ避難民が集中してしまい避難できなかったりなど速やかに避難することが困難な場合があります。
量子コンピュータを取り入れることで、膨大な避難経路から個々の住民へ最適な避難ルートを導き出すことが可能です。現在すでにアプリケーションへの実装を目指し、開発が進められています。
量子コンピュータの実用化における課題

経済や技術の発展において多くの可能性を秘めた量子コンピュータですが、課題がいくつかあります。ここでは量子コンピュータの実用化における課題を3つ紹介します。
● エラー訂正技術の実装
● 暗号技術への脅威
● 極低温環境の実現
それぞれ詳しく解説します。
エラー訂正技術の実装
汎用性が高いとされている量子ゲート方式の量子コンピュータでは、外部からの要因によって量子ビットが不安定になり、エラーが起こりやすいという課題があります。また、量子ゲート数が増えるとエラー発生率が高くなってしまう懸念もあるのです。
現在エラー訂正の対応策として、量子コンピュータと従来コンピュータを掛け合わせたハイブリッド型量子コンピュータの開発が進められています。ハイブリッド型量子コンピュータは、多くの処理を量子コンピュータに任せ、従来コンピュータでは厳密な答えが求められる計算を行うというものです。
それぞれ得意な計算を担当することで、全体として性能を向上させることが可能となります。
暗号技術への脅威
量子コンピュータは暗号技術への脅威になると懸念されています。
現在世の中で使用されている暗号方式(RSA暗号)は素因数分解を用いています。 量子コンピュータは従来コンピュータに比べ素因数分解が得意なため、将来暗号が解かれデータ盗難被害が発生するのではないかと考えられています。
現行の量子コンピュータではまだ主流の暗号解読には至っていませんが、量子コンピュータの技術発展を見越し、新しい暗号方式の開発が進んでいます。
極低温環境の実現
量子コンピュータの稼働には極低温環境が必要です。
量子コンピュータは量子重ね合わせの状態を保持する必要がありますが、この量子重ね合わせの状態は外部からの熱などによるノイズに弱く、ノイズを除去するためには約-273℃という極低温環境を実現する特殊な冷凍機『希釈冷凍機』が必要となります。
また、量子コンピュータが扱う量子ビットが増えれば増えるほど巨大な希釈冷凍機が必要です。量子コンピュータを大規模化するには極低温環境の実現が必須のため、各国で技術開発が進められています。
日本の量子コンピュータ研究

量子コンピュータの研究は海外が主流に見られがちですが、日本における量子コンピュータの研究も後れてはいません。
近年では、短期間で国産の量子コンピュータを複数台稼働させたことが話題になりました。海外の技術に頼らず、国内の技術を用いて量子ビット50個以上のコンピュータを構築した国は、日本以外ではアメリカや中国だけです。
また、量子コンピュータの制御装置を開発したのは日本人であり、日本の知見を元に海外の研究室が研究を進めています。
日本にはアイデア力があるものの、資金調達では海外に後れをとっています。資金調達の問題をいかに解決するかが、今後の日本における量子コンピュータ研究の課題と言えるでしょう。
まとめ:量子コンピュータの今後に注目しよう

本記事では量子コンピュータについて、その概要と実用化、課題について解説しました。
量子コンピュータは従来コンピュータでは困難な計算を可能とし、さまざまな分野での活用が期待されています。災害対策や機械学習の分野で一部実用化が進んではいるものの、量子コンピュータには課題も多く、本格的な実用に向けて日々研究が進められています。
量子コンピュータを用いたシステムの開発を行う未来も近いかもしれません。実用化される将来に向けて、量子コンピュータの今後の発展に、ぜひ注目してみてください。
