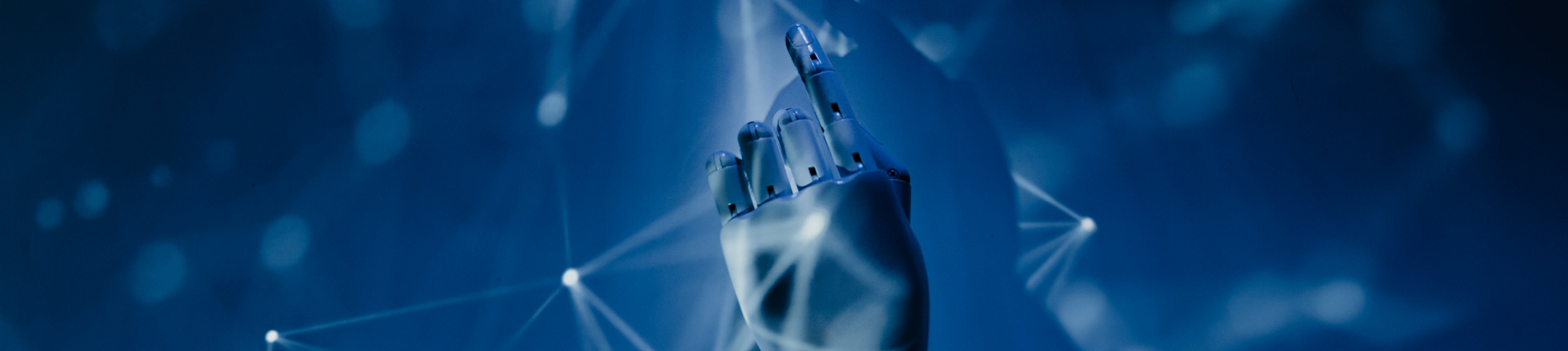掲載日:2024/01/25

『ジェネレーティブAI』とは、『生成AI』とも呼ばれるものであり、AI(人口知能)が学習したデータを基に、オリジナルデータをアウトプットする技術を言います。従来、人間が行っていた活動の一部をAIが実行することで、新たなアイデアやコンテンツを生み出すことが可能です。
『ジェネレーティブAI』はテキストや画像、動画の生成など幅広い分野での活用が期待されている一方で、個人情報の取り扱いや著作権における課題などを抱えています。この記事では、『ジェネレーティブAI』の基本的な紹介とどのような分野で活用できるのかを解説します。
『ジェネレーティブAI』とは

『ジェネレーティブAI』を理解し、うまく活用するためには基本的な仕組みを把握して、これまでのAIとどのように違うのかを知ることが大切です。まずは基本的なポイントから見ていきましょう。
『ジェネレーティブAI』の概要
『ジェネレーティブAI』(Generative AI)は、生成AIとも呼ばれており、様々なデータをAIに学習させることによって、アイデアやコンテンツなどのオリジナルデータをアウトプットするAIを指します。2022年後半から2023年にかけて、急速に話題となったChatGPTも『ジェネレーティブAI』の一種であり、アメリカの大手IT企業をはじめとして多くの企業で生成AIツールが開発されています。
『ジェネレーティブAI』はあくまで膨大なデータを解析し、テキストや画像、動画などのコンテンツを自然言語処理によってアウトプットするものであり、自ら考えて判断を行う汎用型のAIとは異なるものです。また、従来のAIは定型作業の自動化がおもな目的でしたが、『ジェネレーティブAI』では新しいコンテンツの生成が目的となっている点も押さえておきましょう。
ゼロから1を生み出せるのが『ジェネレーティブAI』の特徴
『ジェネレーティブAI』が新たなアイデアやコンテンツを生み出すためには、事前に大量の学習データを与える必要があります。『ジェネレーティブAI』で活用されているデータ分析の方法は、おもにディープラーニング(深層学習)と言われる機械学習の方法です。
ディープラーニングにより、AIは与えられた学習データを基に最適解を導き出すことができ、人の手では生み出せない高度なコンテンツを創出できる可能性を秘めています。単にデータを収集してまとめるだけでなく、それらのデータを基にしてゼロから1のアイデアやコンテンツを生み出せるのが『ジェネレーティブAI』の大きな特徴です。
ただし、生成されるコンテンツの精度については、個人情報や法律面も含め、最終的には人の手でチェックすることが重要であり、『ジェネレーティブAI』で生成されたコンテンツをそのまま使用するのは、リスクが伴う点に注意が必要です。
『ジェネレーティブAI』の主な種類
『ジェネレーティブAI』を利用することで、長文テキストの要約や翻訳、キャッチコピーなどのアイデアの創出、プログラミングのコードを生成するなど様々な使い方ができます。代表的なテキスト生成AIツールとして、OpenAIが開発したChatGPTやGoogleが開発したBardが挙げられます。
また、『ジェネレーティブAI』は文章の生成だけでなく、画像の生成も可能です。テキストで作成したい画像のイメージを伝えることによって、オリジナルの画像を生み出せます。画像生成AIツールとしておもなものは、Stable DiffusionやMidjourneyなどが挙げられるでしょう。わずかな時間で複数のパターンの画像を生成できるため、チラシや本の表紙、動画のサムネイルなど画像を必要とする分野において、作業の省力化に役立つはずです。
さらに、『ジェネレーティブAI』では動画の生成も行えます。動画の作成はコンテンツ制作において難易度が高い部分がありますが、Gen-2などの動画生成AIツールを使えば、品質の優れた動画を生成することができるでしょう。
『ジェネレーティブAI』では、特定の人物の音声を大量に学習させることで、本人の声質とそっくりな声で様々な話をさせるツールも開発されています。音声生成AIツールを活用すれば、本人の声を録音しなくても、データを学習させることであたかも本人が話しているかのような音声を生成することが可能です。
『ジェネレーティブAI』を導入するメリット

『ジェネレーティブAI』を導入することで、どのようなメリットを得られるのかを把握しておけば、より効果的に活用できるはずです。おもな3つのメリットを紹介します。
クリエイティブなアイデアを支援してもらえる
『ジェネレーティブAI』を導入すれば、キャッチコピーやネーミングなどのアイデアを短時間で大量に提案してもらえます。従来はゼロから1を生み出すクリエイティブの領域は人が担う場面が多かったといえます。
しかし、『ジェネレーティブAI』を活用することで、アイデアのたたき台を短時間で得ることができ、それらを人がブラッシュアップすることで作業の省力化が実現できます。
多くのアイデアを求められる作業領域において、大きな効果を発揮するでしょう。
定型業務の効率化を図れる
『ジェネレーティブAI』を活用すれば、前述の通り、テキストの生成や音声認識の機能を使って、議事録の作成や電話応対などの定型業務を効率化できます。『ジェネレーティブAI』に任せる業務内容にもよりますが、これまで時間や手間がかかっていた業務をほぼ自動化することも可能です。
定型業務を自動化できれば、その分のリソースを本来注力すべきコア業務に充てられます。業務フローを見直して、人が担う業務と『ジェネレーティブAI』に任せられる業務を精査することで、生産性の向上にもつなげられるでしょう。
コンテンツ作成のコスト低減が行える
今まで外注していたコンテンツ作成に関する業務を『ジェネレーティブAI』を用いることで内製化できる可能性があります。外注費を抑えられるので、コストの低減につなげられるでしょう。
また、すでに内製化を行っている場合でも、工数の削減を図れます。社内にコンテンツ作成のノウハウを蓄積しながら、コストの低減を目指せる方法として『ジェネレーティブAI』の活用を検討してみましょう。
『ジェネレーティブAI』の活用事例
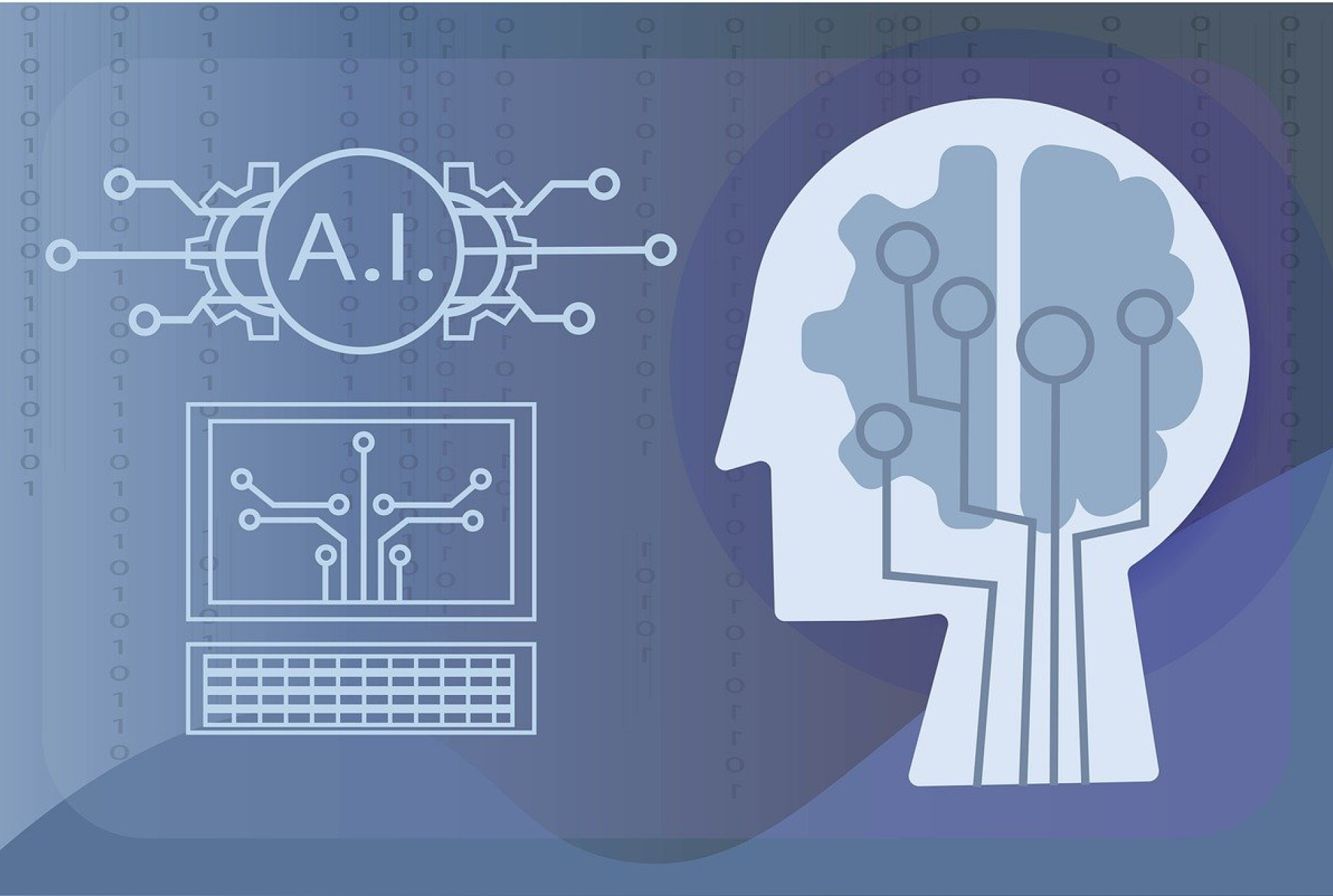
『ジェネレーティブAI』を具体的に活用する前に、実際に使われている事例を参考にご紹介します
必要なデータの抽出
『ジェネレーティブAI』を上手に活用するためには、企業や業界に応じてカスタマイズしていくことが大切です。例えば、社内向けのツールとして活用するのであれば、必要なデータをすぐに抽出できる仕組みを整える必要があるでしょう。
膨大な量のデータを収集してデータベースを構築したとしても、社内データにアクセスをしたときに、人の手で必要なデータを集めるのは時間や手間がかかります。『ジェネレーティブAI』を社内利用の目的で開発することは可能であり、調べたいことを入力するだけで、AIが必要なデータを自動で抽出する仕組みを整えられます。
テキストの要約
文章生成AIツールを活用すれば、長文テキストを要約することができます。文章の要約をAIに指示するだけで、会議の資料作成などを短時間でまとめることが可能です。
また、情報収集のために集めた資料やWebサイトの情報を要約するといった使い方もできます。ただし、出力された情報が正しいものであるかの判断は、人の手で慎重に精査する必要があります。
会議の音声データを文字に起こす
『ジェネレーティブAI』のなかには音声を認識して、テキスト化できるツールも存在します。例えば、会議で録音した音声データをツールにかけることで、自動的に音声データをテキストデータに変換できます。
議事録の作成など、長時間の作業が必要であった分野において、作業の省力化につながります。
プログラミングのコード生成
テキスト生成AIツールを活用すれば、プログラミングのコードを生成することができます。生成させたいコードの内容をツールに指示すれば、わずかな時間で必要なコードを取得できるでしょう。
生成されたコードは、コピー&ペーストするだけで、すぐに活用できます。
背景画像の生成
Webサイトで使用する背景画像の素材作成を『ジェネレーティブAI』に任せることが可能です。Webサイトだけでなく、SNSのアイコン画像などの生成も行えます。
ただし、画像生成を行うときは著作権の問題がないかを事前にチェックすることが重要です。例えば、文化庁では著作権侵害にあたるかどうかを、生成した作品から他人の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じられるか、さらに、生成した作品が既存の著作物に依拠したものでないかという2段階でのチェック要件を示しています。事前に上記に当てはまっていないか確認しましょう。
出典:文化庁「令和5年度著作権セミナー:A I と著作権」P.21
『ジェネレーティブAI』利用時の注意点

『ジェネレーティブAI』を利用することで、人の手で行っていた作業を効率化したり、自動化できたりする部分があります。一方、利用するにあたって著作権などの権利侵害や個人情報の取り扱いといった点で注意も必要です。
『ジェネレーティブAI』を利用するときの注意点を解説します。
著作権などの権利侵害
『ジェネレーティブAI』を利用するときに気をつけておきたい点は、著作権などについて他者の権利を侵害していないかを厳密にチェックする必要があることです。画像生成AIツールを利用すれば、他者のイラストとそっくりなものを生成することも可能なので、結果的に著作権を侵害するリスクが発生します。
『ジェネレーティブAI』を使用すること自体は問題ありませんが、生成されたコンテンツを公開した責任は利用者にあるため、権利関係について慎重な取り扱いが必要です。
個人情報などの取り扱い
『ジェネレーティブAI』は事前に大量のデータをAIに学習させることで、精度の高いコンテンツを生み出せます。しかし、個人が特定できる情報などを入力すれば、データベースに記録されてしまうため、別のユーザーが同じツールを利用したときに個人情報が表示される恐れがあるでしょう。
『ジェネレーティブAI』を利用する際は、個人が特定されてしまうような情報や、企業の機密情報などを入力しないことが肝心です。
まとめ:『ジェネレーティブAI』の基本を押さえて有効活用しよう

『ジェネレーティブAI』は従来のAIとは異なり、事前に学習したデータのみから答えを導き出すだけでなく、AI自身がゼロから1の最適解を生み出す性質を備えています。そのため、これまで気づかなかった新しいアイデアやコンテンツを生成してくれる可能性を秘めており、ビジネスシーンなど様々な場面での活用が期待されていると言えます。
一方、『ジェネレーティブAI』の基本的な仕組みをきちんと把握せずに使用してしまうと、著作権の侵害や個人情報の取り扱いなどでリスクを抱える恐れもあるでしょう。『ジェネレーティブAI』について正しく理解をした上で、どの分野で活用できるかを検討していくことが大事です。自身の仕事で活用可能かどうか試してみましょう。